📙 「あなたのお子さんは本を読むのが好きですか?」

📚本はたくさん本棚に並んでいるのに、どうして読んでくれないの?

おススメの本を買ってきても、見向きもしない!せっかく買ったのに!!📙
多くの親が、読書をしないお子さんに悩んでいます。
読書は学力向上だけでなく、想像力や表現力の育成にも大きく関係します。
こんにちは、きんさちです。
あなたは読書が好きではないお子さんに、どうやったら進んで本を読むようになるのか?とお困りではないでしょうか?
📙うちの子どうして本を読んでくれないの?
「頭のいい子は読書をしている。」とか「成功している人は小さなころから読書をしていた」という話をよく聞きます。
あなたは我が子が読書をしないことに不安を感じていませんか?
「うちの子どうして、本を読んでくれないんだろう…」
実はこの悩みはあなただけではないんです。ほとんどの子どもが読書をしていません!

教育家庭新聞のホームページに「約半数の子供の読書時間が0分」とありました!
(もっと詳しく知りたい方は、教育家庭新聞ホームページhttps://www.kknews.co.jp/news/20231023o02からご覧ください。)
ほとんどのご家庭で、本を読まないお子さんに親は困っているんです💦
しかし教育関連の本や、動画、ブログに講演会など、あらゆる教育の場で「本を読みましょう!」と多くの方がおっしゃっています。
今回はどうにか子どもに本を読んでもらいたい!をという悩みを解決する記事をご準備いたしました!
- 子どもが読書が好きではない原因は何なのか?
- 読書習慣をつけるとどうなるのか?
- 春休みにチャレンジ!読書をする習慣をつけるには?
この記事であなたのお子さんの「本を好きになるきっかけ」になることを願っています。
まずは、読書を好きになれない原因を探ってみましょう!
📙子どもが読書が好きではない原因は何なのか?

まず、一般的に子どもが読書を好まない理由を考えてみましょう。
あなたは、お子さんの本を読まない理由が思いつきますか?
1. 小学生は本を読むのが難しいと感じている?
小学生のお子さんは、知識が少なく、「本を読むのは難しいし、楽しくない。」と思っている場合があります。
文章の中に出てくるモノや事柄に対する知識がなかったり、文章の意味を想像できず、内容を理解するのに時間がかかったり、『読書は意味が解らないので、楽しくないもの』と感じ、読書自体が苦痛に感じられることもあるようです。
例えば、「地下鉄のり場は、たくさんの人が並んでいた。」という文章があったとします。
地下鉄のある地域に住んでいる子どもは地下鉄がどんなものかがわかるので、簡単に想像することが出来ます。
では地下鉄の無い地域に住んでいる子どもがこの文章を読むとどうなるでしょうか?
まず
地下鉄って何だろう…
何て読むのかな?
地下に鉄が埋まっているところに行くバスの乗り場かな?
すんなり読み進めることができません。
成長しその過程で様々なことを学び知らないと、するすると文章を読んで書いてあることを知っていないと、文章を読むことは困難になってきます。

いろいろな体験をしたり、インターネットで調べたり、テレビを見たりと子どもに様々なことを興味を持つと、どんどん言葉やもの、習慣や常識を学びます。
特にお子さんが興味があるものにつなげて調べたり、体験型学習を経験させたりと、色々な知識をつけると、本を読むときに頭に状況などが浮かびやすくなるため、本を好きになる可能性は高いです。
2. 興味のある本がない
お子さんが興味のあることは何でしょう?
ちなみに我が家の息子は、小学生低学年の時の興味の大半は、「魚」「ポケモン」と「ムシキング」でした。この三つが載っている本は分厚くてもいつも持ってました。
文字を読む習慣をつけることが大事ですので、文章になっていなくても、図鑑や攻略本でも大丈夫です!
まずは文字を読んでもらうことに注力してみてください!
そして少しずつ長い文章や、お話に興味を持ってもらいましょう。
気づくと、お話を読みはじめているかも…📚
3. 読書よりも楽しいことがある
読書が宿題や義務のように感じられると、楽しさを見出せず、避けてしまうことがあります。
⚽スポーツをするのが
好き!
🎮ゲームをするのが
好き!
🐶🐱動物と遊ぶのが
好き!
あなたのお子さんが読書をするよりも、楽しいと思うことがあるなら、無理に「本を読みなさい!」と言うと逆効果になってしまうことがあります。
⚽スポーツをするのが好きなお子さんには、スポーツ雑誌や主人公がスポーツをしている物語を。
🎮ゲームをするのが好きなお子さんには、ゲームの攻略本やゲーム感覚で進む推理小説を。
🐶🐱動物と遊ぶのが好きなお子さんには、動物の図鑑や、飼育方法、動物が出てくる物語を。
こっそり買って、目につくところに置いておきましょう。
あの手この手でお子さんの興味をひいてみて下さいね!
では次は読書をすることで得られる素晴らしい効果をご紹介します!
📙読書が子どもに与える5つの素晴らしい効果

昔から、読書がいいもであると言われています。
様々な成功体験や、成功している人が行っている習慣の一つです。
大人でも読書を習慣にしましょう。と言われていますので、子どもならなおさらです。
読書が子どもに与える影響は計り知れないと言われています。
小学生の読書習慣がもたらす効果をさらにご紹介!
読書習慣を身につけることで、子どもたちにはさまざまな効果が期待できます。
以下にその主な効果を挙げていきましょう。
学力向上 - 読書は学力を高めるためにとても役立ちます。
本を読むことで、新しい言葉や文章の読み方を学ぶことができます。
物語を読んでいると、普段使わない言葉に出会うことがあります。
例えば、物語を読んで、「あっ、こんな考え方があるんだな」「こんな風に言ったらかわいそうだよね」など、お子さんが今まで感じなかった意見や感情もでてきます。
本を読むことで、新しい言葉や文章の読み方を学ぶことができますし、読書は語彙力や読解力を高めるため、学力向上に直結します。
これにより、国語のテストでの点数が上がるだけでなく、数学や理科の問題を理解するのにも役立ちます。問題文を読むとき、正しく内容を理解して答えを導き出すには読解力が必要です。
読書をすることで、新しい知識をつけたら、子どもは使ってみたくなりますよね。
知っていることを話したくなるのは人間の習性なので、新しいコミュニティに足を踏み入れる一歩になるかもしれません。
それにともない、コミュニケーション能力が身に付いたり、お子さんが好きな事や、話をする機会が増えたりと、お子さんにも良い事ばかりではないでしょうか。
集中力の向上 - 本を読むことで集中力が高まります。
本を読むことで、集中力が養われると言われています。
本を読むときは、ページをめくりながら文字を追い続ける必要がありますよね。
好きな小説を一気に読み進めると、長時間集中している自分に気づくでしょう。
この集中力は、将来の勉強や仕事に役立ちます。
例えば、試験勉強をするときに、長時間集中して問題を解く力がつくのです。
想像力と創造力の育成 - 読書は想像力を豊かにします。
読書は子どもたちの想像力を豊かにします。
物語を読むと、登場人物や情景を自分の頭の中で思い描くことが求められます。
例えば、ファンタジー小説を読んで、魔法の世界やキャラクターを想像することで、創造力が刺激されます。
このように、読書を通じて自分の想像力を広げることができ、将来的には自分自身のアイデアを生み出す力にもつながります。
感情の理解と共感力の向上 - 他人の考えを想像する力が身に付きます。
登場人物の感情に共感することで、他者の気持ちを理解する力が育まれます。
物語の中で、登場人物が悲しんだり喜んだりする場面に触れることで、他の人の気持ちを理解する力が高まります。
例えば、友達が困っているときに、その気持ちを理解し、助けてあげることができるようになります。これは、学校や社会での人間関係を良好に保つために非常に重要なスキルです。
共感力が高いと、友達とのコミュニケーションがスムーズになり、より良い関係を築くことができます。
さて、読書には素晴らしい効果をご紹介しました。
お次はこの効果を得るための方法をお伝えしていきます。
📙子どもが楽しく読書を続けるための実践方法

では、お子さんに本を好きになってもらうために、具体的な方法を紹介していきましょう。
1. 👶ベビーステップ👣のすゝめ(小さなステップから始める)
「まずは1日1分から始めてみましょう!」
読書をしているご家庭でも、読書の平均時間は15分ほどです。
小さな目標を設定することで、子どもが負担に感じず、達成感を得られます。
朝起きてすぐ、帰宅後すぐ、お風呂の後すぐ、夕ご飯の後すぐ、歯を磨いた後すぐ、寝る前に…と、今すでに習慣になっていることの後に行うと、習慣になりやすいのでおすすめです。
「1分とか、読む意味なくない?」と思ったそこのあなた!
1分読んで、ちょうど気になる内容にさしかかったら、1分で読むのをやめます?
いや、きっとやめないはず。
きっと先も読んで、気づくと10分ぐらい過ぎている時があったはず!!
ちょっと強引な考え方ですが、お子さんにもこの方法をやってもらいましょう。
興味のある本を読んでいるのに、「1分間毎日読書」と言われて、本当に1分で終わるお子さんはあまりいません。
最初のうちは「もう1分過ぎたよ~!まだ読んでるの~?」と声掛けをして、息子が「も~話かけんで!!」と迷惑そうに言うのが、私は楽しかったです😊
2分でも3分でも興味をひく文章があれば続けて読みたくなる人間のしくみを活かして、読書習慣を身につけて行きましょう。
万が一、本を読むことに興味が持てずに本当に「1分」で終わってしまっても、大丈夫です。
1ヵ月で30分読んだことになるので、読まないよりはいいし、毎日読む習慣は身につきます。
この習慣が、中学校、高校、大学生、大人になった時に、大きな力を発揮してくれます。
2. どんな本を選んだらいいの?
最初は短い物語や絵本から始めると良いです。
お子さんが興味を持ちそうなキャラクターやテーマの本を選んでみましょう。
よくわからないときは、人気のある本を選んでみましょう。
好きなキャラクターやジャンルを考慮することで、読書へのモチベーションが高まります!
ちなみに息子が低学年の時はアーノルド・ローベルの「がまくんとかえるくん」シリーズが大好きでした!
アーノルド・ローベルの「がまくんとかえるくん」シリーズ
もともと保育園の時に読み聞かせをしていた本ですが、ひらがなをすらすらと読めるようになったら自分で読み出しました!
がまくんとかえるくん、ふたりの間で繰り広げられる、くすっと笑えて、どうしてかな?なにがあったのかな?それは悲しいね…などたくさんの要素がつまったエピソードに我が家ではたくさんの会話が生まれました。
「がまくんとかえるくん」シリーズは、お子さんが平仮名をなんなく読めるようになったら、ぜひ読んでもらいたい一冊です。
 |
ふたりはしんゆう がまくんとかえるくん ぜんぶのおはなし [ アーノルド・ローベル ]
|
こちらもオススメ!
伝記シリーズ(まんが)
我が子がドはまりしていたのが、伝記シリーズ。
我が子の時代なので、集英社さん版の伝記シリーズを読んで、何者かになってみたい野望を抱いてました笑
まんがは時代の背景が「絵」で確認できるので、知らない事を容易に知るためにはおススメの本です。
歴史の授業を受ける前に、時代背景を知るためには持ってこいの本です。
3. 楽しく読むための工夫をしましょう
「図書館や本屋に一緒に行く」 子どもが自分で本を選ぶ楽しさを体験できるよう、定期的に図書館や本屋に足を運びましょう。
自分で本を選ぶことで、子どもは「本を選ぶ楽しさ」を感じ、次第に読書への興味を深めていきます。
「読んだ本を家族で話し合う」 読書後に感想を共有することで、読書の楽しさを実感させるとともに、コミュニケーションの機会が増えます。
では、読書習慣と学力にはどのような関係性があるのでしょうか?
✍読書習慣と学力の関係 全国学力・学習状況調査のデータを分析!
読書をする子どもとそうでない子どもでは、どのくらいの学力の差があるか気になりますよね?
文部科学省のホームページに調査結果が載っていたので、要約してみました!
内容が長かったので、私が気になった所や、主に重要だと思われるところを要約、抜粋しています。
他にも気になるかたは、原本をダウンロードして、ご覧ください。
データ参照:文部科学省 以下のページからPDFをダウンロードできます。
平成21年度 文部科学省 委託調査研究 「学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究」
C.読書活動と学力・学習状況の関係に関する調査研究 分析報告書
(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/045/shiryo/attach/1302195.htm?utm_source=chatgpt.com)
【概要】
読書活動と学力・学習状況の関係を明らかにするために、全国学力・学習状況調査のデータを分析したものです。
調査対象は、小学生約114万人、中学生約107万人で、読書時間、図書館利用頻度、読書の好みと学力の関係を分析しています。
主な結論は以下の通りです。
読書好きの子どもは学力が高い
- 読書が好きな子どもほど、すべての教科で正答数が高い。
- どの学力層においても、読書好きの子どもは正答率が高い傾向にある。
読書時間の長さと学力の関係
- 1日に10分以上の読書が学力向上に有効であり、小学生では「10分以上2時間未満」、中学生では「10分以上1時間未満」の読書時間を持つ子どもが最も高い学力を示した。
- 2時間以上の長時間読書は、学力向上にはつながらない場合がある。
学力の低い層(学力層D)では、長時間読書する子どもが多いが、同時にテレビやゲーム、インターネットにも長時間を費やしており、読書の質が低い可能性がある。
- 学習習慣との関係
学力の高い読書好きの子どもは、計画的な勉強をしていることが多い。
特に小学生では「計画的な勉強をする子ほど読書時間を確保している」傾向があった。
1. 読書量と学力の関係
1日10分以上の読書を続けた子どもは、読書をしない子どもよりも語彙力が2倍以上高い?
読書量と学力の関係をまとめると以下の通りです。
- 読書好きの子どもほど、すべての教科で正答率が高い
- 特に国語の学力との関連が強く、読書時間10分以上1時間未満の子どもの正答数が高い
- 計画的な勉強と読書を組み合わせることで、さらに学力が向上する
結果、適度な読書をすると、学力も良くなる傾向にあるようです。
2. 読書習慣の形成
子どもの頃に読書習慣があると、大人になっても学び続ける力が身につきます。
読書を通じて得られる情報処理能力や理解力は、学業だけでなく、仕事や日常生活でも大いに役立ちます。
さらに、読書習慣が身についた子どもは、自己学習や問題解決能力を高めることができ、生涯学び続ける力を育む基盤となります。
小学生に読書習慣をつけることはとてもいい習慣だということがこの調査でもわかりました。
というわけで、ぜひともあなたのお子さんにも、読書習慣を身に付けてもらいましょう!

世の中が目まぐるしく変化する時代です。
むかしは一つの技術を習得すれば食べていけると言われていましたが、今は一つの技術がいつまで通用するのかが問題になっています。
リスキニングという言葉もあちらこちらで耳にするようになりました。
今の子どもは大人になっても学びながら成長していかないと、「食うに困る」ことになってしまいます。子どもの家から本を読み、学習する習慣をつけていたほうが未来への大きな投資になるでしょう。
🌸 春休み中に読書習慣をつけましょう!

対象:小学生(1年生~6年生)
目的:春休みの約2週間で「毎日読書する習慣」を身につける
ポイント
- 無理なく楽しく読書に取り組む
- 興味のある本を選ぶ
- 短時間から始め、徐々に読書時間を増やす
📚 1週目(導入期) – 読書の楽しさを体験する
🌱 好きな本を選ぶ
まずは「好きなこと」をテーマに本を選びましょう。動物が好きなら動物の本、おばけが好きなら怖い話など、興味のある本を見つけることが大切です。本屋さんや図書館に行くのもおすすめです。
📖1分だけ読んでみよう
いきなり長時間読むのではなく、まずは1~10分だけ本を開いてみます。「少し物足りない」くらいがちょうどいいです。
🗣 親子で読み聞かせタイム
親が子どもに読んであげたり、子どもが親に音読したりして、本を共有する楽しさを感じます。
🎨 読んだ本のシーンを絵に描こう
読書をした後に、印象に残ったシーンを絵に描いてみましょう。文章だけでなく、視覚的に本の内容を楽しむことができます。
💬家族に本の感想を話す
「どこが面白かった?」と聞かれることで、内容を思い出しながら話す練習になります。
🎶 好きなセリフを読んでみる
本の登場人物になりきって、好きなセリフを読んでみましょう。感情を込めて読むことで、物語の世界に入り込みやすくなります。
🎯 短い本を1冊読み切る
達成感を得るために、短めの本(絵本や短編集)を1冊読んでみます。「本を読み終える」経験を大切にします。
📚 2週目(定着期) – 読書を習慣化する
📌 寝る前に読書タイムを作る
毎晩寝る前の1~15分を読書時間にします。「寝る前に本を読む」習慣をつけることで、春休み後も続けやすくなります。
📖図書館や本屋で次の本を選ぶ
「次に読む本」を子ども自身が選ぶことで、主体的に読書をする意識を育てます。
📚 新しいジャンルに挑戦する
普段読まないジャンルの本に挑戦してみましょう。例えば、少しだけ気になる推理物語が好きなら科学の本を読んでみるなど、新たな発見を楽しみます。
📝 読書日記を書いてみる
1行だけでもOK!「面白かったこと」や「新しく知った言葉」をメモすることで、読書の記憶が深まります。
📢 12日目:おすすめの本を紹介する
家族や友達に「この本が面白かったよ!」と伝えることで、読んだ内容を整理し、伝える力も育ちます。
🎭 本の内容を劇にしてみる
家族や兄弟で、読んだ本をもとに簡単な寸劇をしてみましょう。楽しみながら、物語の理解が深まります。
🎉 春休みの読書記録を振り返る
「何冊読んだかな?」と振り返りながら、達成感を味わいましょう。「次に読みたい本」を決めると、春休み後も読書習慣が続きやすくなります。
🎯 春休みの2週間!無理のないように試してみて!
- 1週目(導入期):読書の楽しさを知る
- 2週目(定着期):毎日少しずつ読書を続ける習慣をつける
全てを行う必要はありませんが、できるだけ試してみてください。
きっと、春休みの間に読書を自然に楽しめるようになり、学校が始まっても本を読む習慣を続けることができるようになります📖✨
📙本を読む子は頭が良い!家に本があるということ
「本を読む子は頭が良い」と言われるように、読書は知識を増やすだけでなく、思考力や判断力を養います。家に本がたくさんある環境を整えることも、読書習慣を促進するために重要です。
本棚を整える: 家の中に本棚を設け、子どもが自分で本を選べるようにしましょう。
視覚的に本が見えることで、自然と手に取る機会が増えます。
多様なジャンルの本を揃える: 物語、科学、歴史、漫画など、さまざまなジャンルの本を揃えることで、子どもたちの興味を引き出します。特に、好きなキャラクターが登場する本は効果的です。
読書は子どもたちの世界を広げ、さまざまな知識や経験を提供します。
以下の方法も、読書を好きになる方法の一つです。
読書のテーマを広げる: 旅行や異文化についての本を読むことで、子どもたちの視野が広がります。
新しい世界を知ることで、興味や好奇心が刺激されます。
読書を通じたディスカッション: 読んだ本について家族で話し合うことで、理解を深めるとともに、意見を表現する力も育まれます。これにより、考えた事を言語化する能力が身に付いたり、コミュニケーション能力が向上します。
読書の成果を実感させる: 読書を通じて得た知識や感情を実生活に活かすことで、子どもたちは読書の重要性を実感します。
例えば、読んだ本の内容を使って家族の中で重要な事柄を行ったり、学校のプロジェクトを行うなど、実践的な経験を積むことができます。
まとめ

読書を好きになることで子どもの学力や想像力が高まることをご紹介しました。
私たちが、「読書をさせよう!」と思っても、子ども自身が「読みたい」と思わなければ、どんなに良い本があっても進んで読むことはないですよね。
まずは、読書に興味を持たせるために、「子どもが関心を持っている分野」から始めることが大切であるとお伝えしました。
図鑑やマンガで学べる本、ゲームに関連する情報本など、子ども自身が楽しめるような内容の本を探してみましょう。
また、読書を楽しむための機会の一つとして、親子での「共同読書」や1年生のうちは「読みきかせ」も推奨します。
また、本を読むことで子どもが知らなかったことを一緒に調べたり、風景を体感できるように、読書の後に親子で話す時間を作るのも良い方法ですね。
そして、長期の休みは新しいことに挑戦しやすい機会です。
この春休みに読書習慣を身に付けることにチャレンジしてみませんか?
ぜひ、お子さんが進んで本を読むようになる、読書したことを楽しく話してくれる、そんな家庭の風景を実現してください。
子どもの世界が広がるそんな大切な機会を、この春休みから作っていきましょう!

この記事が、お子さんの素晴らしい未来を切り開く手助けとなりますように!
最後までお読みいただきありがとうございました。


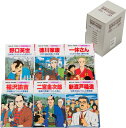








コメント